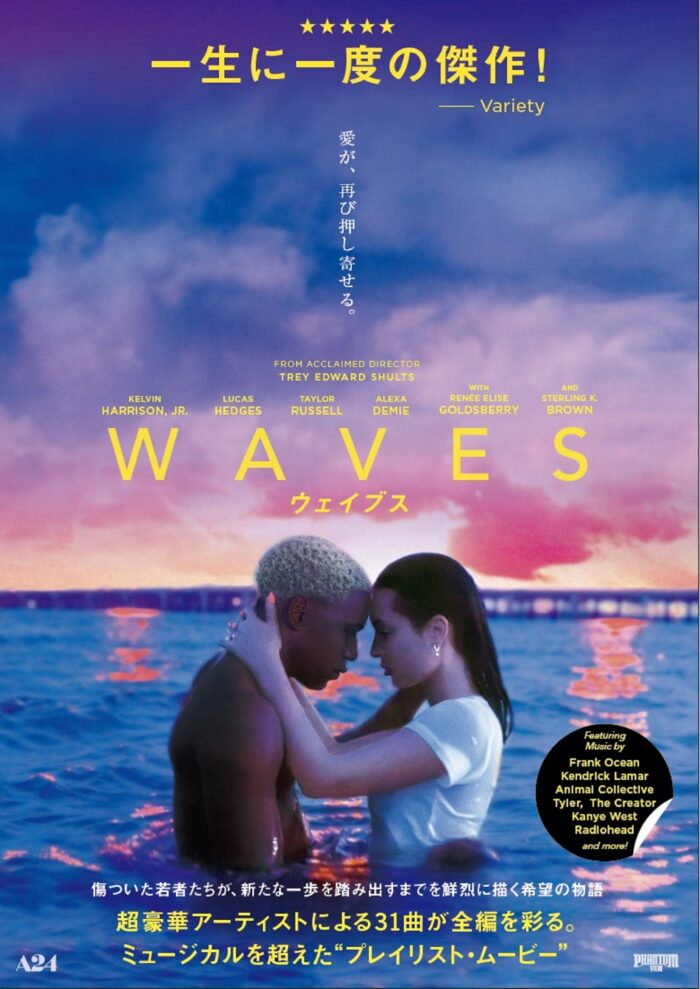喪の果てへの旅 黒沢清『岸辺の旅』
2022/02/25
死んだ人たちの伝達は生きている
人たちの言語を越えて火をもって
表明されるのだ。
- T.S.エリオット『四つの四重奏曲』より
西脇順三郎訳
1.「水で、という気はしてたの」
柔らかい陽光が、穏やかな微風に揺れるレースカーテン越しに流れ込んでいて、静かに部屋を満たす。小鳥のさえずりが聴こえる。たどたどしいテンポでピアノを弾く少女は、いくつかの小節を弾き終えると頼りなさげな表情で振り返る。
「もう一度最初から。焦らないで、ゆっくり」
ピアノ教師である薮内瑞希(深津絵里)は、少女の傍らにそっと歩み寄り、彼女の不安を和らげるように優しい声でそう告げる。少女の顔の高さに合わせるため、腰を曲げかがんだ姿勢になった瑞希の横顔は、肩まで伸びた黒髪で隠されていて、形の良い鼻先と唇だけが覗いている。
黒沢清の諸作において、死者(あるいは死)の表象とは、鮮明に映されてしかるべき人物の顔が朧げにしか映されないことで示されてきたのを思い出す。『岸辺の旅』の主人公である瑞希の顔が初めて近い距離で示されるショットでもまた、彼女の表情が判別することのできないアングルにキャメラが置かれているからだ。まだ映画がはじまって間もない冒頭部分、それもピアノの練習風景という穏やかな日常的シーンでありながら、たった一つのショットによって濃密な死の気配が画面いっぱいに立ち込めていく。黒沢清の作品を見ることとは、それがいつの時期のどんなジャンルに属するものであれ、この濃密な死の気配を全身で受け止める体験に他ならないということは誰もが知っているだろうが、それでは『岸辺の旅』の観客もまた、たとえば『CURE』のように人間心理の底知れぬ暗闇に深く埋没する恐怖を味わうことになるのだろうか。
たしかに、続くシーンでようやく表情を露わにした瑞希の顔貌はどこか生気を欠いていて、まるで自分が死んだことに気づいていない死者がスーパーで買い物をしているかのように見えるかもしれない。帰宅し、白玉団子を調理する瑞希の後ろ姿も生活的な躍動を見せることなく、キッチンの明かりだけが灯された暗い室内でただじっと静止し、二粒ばかりの団子が茹でられるのを冷たい表情でみつめるばかりだ。
ところが、次の瞬間、ひとつのショットが事態の変化を告げる。団子をみつめる瑞希をアップショットで捉えたシネマスコープサイズの画面が、俄かに、そしてゆっくりと左方向へパンしはじめるのだ。キャメラは瑞希を画面の右端に追いやり、左側の空間が大きく映されるが、そこには誰もおらず、明かりの乏しい部屋の片隅だけが映されている。誰もおらず何もない空間への不気味なパンショット。その意味が理解できるのは続くショットである。何のきっかけもなく、瑞希は何かに気付いたかのように後ろを振り向く。すると、3年もの間失踪していた瑞希の夫、優介(浅野忠信)が前述のパンショットには誰もいなかった暗い部屋の片隅に靴を履いたまま立っていて、そればかりか自分はすでに死んでいると瑞希に告げもする。
ここで驚くべきは、死んだ優介が亡霊となって不意に帰還したことそのものではない。自らが死者であると告げる夫を前にした瑞希が、ほとんど驚きも喜びもせず、恐怖の反応すら些かも見せないことなのだ。それはまるで、カール・テオドール・ドライヤーの『奇跡』で、死者の蘇生に立ち会った家族が一切騒ぎ立てることなく、ごく穏やかにその事態をただ祝福することの感動とよく似ている。瑞希もまた、優介が死者として帰還するという事態に立ち会いながら、その超常性を一切疑うことなく紛れもない現実として受け入れ、何よりまず靴を履いたまま部屋にいる優介をたしなめもしてしまうからだ。
「不思議な感じだったな。あっという間なんだよ。一歩踏み込んで、ことがはじまるともう引き返せない。あっぷあっぷしてるかと思うとぐいーと引き込まれて」
「水で、という気はしてたの」
「でも、全然苦しくなかった」
「そう、よかった」
まるで他人事のように落ち着き払った調子で自らの死の瞬間を語ってみせる優介に対し、次第に語調を強め、声を震わせてゆく瑞希は、優介の死に苦しみがなかったことを祝福しさえし、冷たいままだったその表情にも生者としての人間的な熱量を取り戻していく。亡霊である優介が一瞬でも姿を消すと、安堵するどころかむしろ声を荒げ、再度の不在を阻止せんと努める。現世での存在が長続きしないことを示唆する優介を押し倒し、抱擁し、いつまでもここにいて、と強く訴えかけもする。
つまり、これら一連のシーンで重要なのは、それまでの多くの黒沢作品では底なしの恐怖を準備した「濃密な死の気配」が、むしろここでは絶望のただなかに冷たく沈滞する人間の感情に生の熱量と愛の歓びを蘇生させる「予感」として機能することにあるのだ。映されない顔、不気味なパン、死者の出現、夫の死に方をなぜか確信していたこと。理由なく繰り出されるこれらの不穏な要素は、物語順序の論理に先立つ啓示として降臨する。そして、その不穏な啓示はかえってことごとく瑞希の生を肯定し、鼓舞することになるのである。
微風に揺れるレースカーテン越しに流れ込んできた柔らかい陽光が、リビングルームの白い絨毯の上に倒れこんだ二人を包む。優介は、生前世話になった人たちに会うための旅に出るという。みっちゃん、俺と一緒に来ないか?
「長くなるの?」
「なる」

2.「どこだかわからないけど、いかなくちゃならない」
彩度の浅い画面の中でひときわ映えるオレンジ色のコートを着た男と、それとは対照的な緑色のスカートを履いた女が、神奈川県小田原市郊外のとある駅に降り立つ。電車の中では見知らぬひとりの少年から謎めいた視線を送られ、無言のまま両手を膝に置かれもした男と、それに戸惑いつつ寄り添っている女というこの「奇妙な二人組」は、いま、彼らよりも輪をかけて奇妙な一人の老人を探している。
ここでもまた「予感」に導かれるように理由なく、オレンジ色のコートを翻して後ろを振り向いた優介は、バイクに乗って新聞を配達して回る島影(小松政夫)の姿を発見する。生前の優介が新聞配達員として働いた際、世話になっていた老人である。水色のヘルメットを被った島影は、二人を彼の仕事場兼住居に招き入れる。たったひとりでそこに暮らす島影との会話は絶妙に嚙み合わず、かつての瑞希同様彼もまたどこか現実的な生の感触が希薄に感じられる。島影に勧められるまま、そこに泊まり込むことになった二人は、夜になると寝支度をはじめる。顔を向き合わせることなく各々の作業に取り組みつつ話し続ける二人の会話がふと止まると、理由なき「予感」に二人は振り返り、顔を見合わせる。
「島影さんはね、俺と一緒なんだよ」
「えっ、どうして」
「わかるんだよ、大抵は」
理由なき確信とともに、島影がすでに死んでおり、かつ、彼は自分が死んでいることに気付いていないと断言する優介を捉えたアップショットは、きっかけ無しにゆっくりと彼の左上方のドアへと移動してゆき、しばらくすると、ドアの曇りガラスの奥を島影らしき人物の不鮮明な姿が横切る。
小津安二郎の『非常線の女』で、ギャングの岡譲二とその情婦である田中絹代の部屋へ警察が踏み込む直前に、それを予期したかのようにキャメラがドアの方へ前進移動するショットと相似形にあるともいえるこのショットは、それ自体で映画的緊張感を画面いっぱいに行きわたらせもするだろう。
しかし、それにも増して重要なのはその後に続くショットだ。不穏な夜を経て、翌朝目覚めた瑞希が、まだ眠りから覚めていない優介の口元に顔を近づけてゆき、接吻するほどの近さに達したとき、唇ではなく耳を向けて彼の寝息を確かめ、安堵するというショットのことである。あの不穏な夜のショットが、この愛情の緊迫感と充実した光に満ちた幸福極まりないショットを「予感」したのである。
自らの現世での存在が終わりを迎えようとしていることを「予感」する島影が「どこだかわからないけど、いかなくちゃならない」と語る言葉の通り、『岸辺の旅』のキャメラもまた、物語順序の論理を逸脱し、それに先立って運動を開始するのである。
さらにここでは、それまで反復された、不穏が幸福を準備するという構造の逆転現象さえ起ってしまう。
不穏な「予感」に打ちひしがれ、夜の公園で酔いつぶれた島影を優介がおんぶして家に連れ帰り(死者が死者を背負うという光景が、ただそれだけで素晴らしい)、瑞希もそれを手伝って暗い部屋のベッドに島影を降ろすと、完全に理由を欠いた光がゆっくりと壁一面に貼られた紙の花を照らし上げてゆく。
優介の不意の帰還に瑞希が現実的な驚きを見せなかったように、ここでの二人も、それまで黒い影に覆われていた壁が唐突に明るくなってゆくという事態に一切反応することなく、ただ島影のライフワークの成果に圧倒されるばかりだ(この説明不在の光によって露わにされたあまりにも豊かな色彩に包まれつつ、唇をわずかに開きながら、言葉なしに紙の花をみつめる深津絵里の横顔のショットは、デジタルによって撮影されたあらゆるショットの中で最も美しいもののひとつと断言してよい。これほどの画面をデジタルで撮りえた映画作家など、世界を見渡しても『ヴィタリナ』のペドロ・コスタぐらいしか見当たるまい)。
その翌朝、瑞希は、彼らがそれまで暮らしていた家が廃墟と化している様を目撃することとなる。島影の姿も見当たらない。島影がすでに死者でありつつそれに気づかなかったのと同様に、家もまたみずからが廃墟になっていることを知らなかったのだろう。壁に貼られた紙の花は色彩を失い、ぱらぱらと音をたてて崩れ落ちてゆく。
ところで、荒れ果てた室内を映し出してゆく無人のフィックスショットの中のひとつに、割れた鏡のショットが紛れ込んでいて、小津安二郎における無人の部屋の鏡のショットがふと頭をよぎる。優介が瑞希との性的な接触を拒むことで『晩春』を連想させもするシーンの直後に置かれたこのショットと、シーン全体に濃密に貼りつく小津安二郎の気配は、続く第二の旅へ引き継がれることとなるだろう。

3.「もう一度最初から、優しくなめらかに、自分のテンポで」
『岸辺の旅』で最も重要な箇所に思われるのは、優介がかつて働いていた中華料理屋の女将、神内フジエ(村岡希美)や、優介の生前の浮気相手であった松崎朋子(蒼井優)と瑞希が対話するシーンである。この二つの対話では、人物の正面にキャメラが置かれることで画面に尋常ならざる強度を漲らせるからだ。
中華料理屋の手伝いに励む瑞希は、久々に宴会の予約が入ったので、フジエとともに長いこと使われておらず倉庫と化していた広間を片付けている。そこに一台のピアノを発見した瑞希は、彼女が幼いころピアノ教師から告げられたという言葉をフジエに話す。
「自分の音を聴きなさい。耳をすまして、注意してよく聴きなさい。どんなに嫌いでも、あなたの音が、あなたなんです」
この台詞の箇所でまず最初の正面切り返しが現れる。にこやかな表情で瑞希が話すのと対照的に、それを聞いているフジエは表情を硬直させ、口を閉ざしたまま返事をせず、作業をする手も止まっている。この奇妙な切り返しの意味がわかるのはその後のシーンである。
宴会の準備を続ける中、瑞希はふとピアノの上に置かれた楽譜を見つける。『天使の合唱』と題されたその楽譜を開くと、職業的な習慣からか瑞希はピアノの椅子に座り、その曲を弾きはじめる。すると、血相を変え走りよってきたフジエが瑞希の行動を厳しい口調で非難する。ちょっとなにやってんの、やめてよね、勝手にそういうの。誰もいない広間で少しピアノを弾いてみただけなのだから、この非難はあまりに唐突で理不尽に思えるのだが、瑞希は深く謝罪してみせる。本当にすみませんでした。こういう楽器って、持ち主の身体の一部みたいなところがありますから。瑞希の誠実な謝罪ぶりに冷静さを取り戻したフジエは、自らの過去を話しはじめる。
「私ね、8つも歳の離れた妹がいたの。私が18のときだったから、彼女は10歳。もともと腸が弱い子でね。痛い、痛いって苦しんで。あっという間に死んじゃったの。その楽譜の曲、『天使の合唱』、あの子ずいぶん気に入ったみたいで、勝手に一人で何度も練習して。ほんと、何度も、何度も、嫌になるくらい。ちょっと上手くなったかな、と思うと、また元のたどたどしいテンポに戻ったりして。すっかり耳にこびりついちゃったのよ。それでね、私、一度だけ彼女のこと、ひどくひっぱたいたことがあったの。ひとに聴かせないでよそんなピアノ、自分でわかるでしょ、ニ度と私のピアノに触らないで、って。10歳の子供に。どうかしてたんだ。いろいろ迷ってた時期でもあったしね。それからすぐ、妹は死んじゃった。だから私もピアノ辞めたの。で、親はそれ処分するって言ったんだけど、私はなぜか反対してね。ずっと実家の片隅に置いてあったのを、ここに越して引き取ったの。ほんと、どうでもいい話。でも、そんなどうでもいいことが、凧糸みたいにいっつも私の足に絡みついてて、歳とればとるほど、もう一歩も前に進めないって思うくらい頑丈に、私を過去に繋ぎ留めてるの。ほんの一瞬でいい。私、あのころに戻りたい。それで、心からまこちゃんに謝りたい。叩いてごめんね。ピアノ、弾きたかったんだよね。私がいつも弾いてるの、羨ましかったんだよね。お姉ちゃんのこと、許してね。また天国で会おうね。私はすっかりおばさんになってるけど、ちゃんと覚えててね。後悔してもしてもしきれなくって、あれからもう、30年も経ってしまった」
瑞希と話していたはずのフジエは、いつのまにか、亡き妹に話しかけている。瑞希が子供にピアノを教えるときそうするように、フジエも腰を曲げ、かがんだ姿勢で、誰もいない空間へ向けて語りかける。陽光が落ちる。広間は暗闇に飲み込まれそうになる。
独白を終え、姿勢を崩しうなだれたフジエの眼前に、赤いチェック柄のワンピースを着た幼いままの妹が現れる。フジエはピアノの方を振り返る。瑞希は優しい表情と声で見守るように、フジエの妹をピアノに招く。彼女は『天使の合唱』を弾きはじめるが、たどたどしいテンポで上手く弾けず、途中で断念してしまう。
「もう一度最初から、優しくなめらかに、自分のテンポで」
瑞希の言葉を受け取った彼女は、ふたたび『天使の合唱』を弾く。生きているころにはそのように弾くことができなかっただろう完璧なテンポで。美しいピアノの音色が広間に響きわたる。レースカーテンが微風に揺れている。床に座り込んだままのフジエは、静止したまま妹の姿をみつめている。
このときキャメラは、フジエの正面から全身を映したショットに続き、同方向からフジエの胸元の上をアップで捉える。フジエの瞳は涙で濡れ輝いている。あの「奇妙な切り返し」の正面ショットが、いまここで反復されているのだ。この正面ショットがいかに強靭なものか、言葉で説明することはできない。小津安二郎や、小津を敬愛し正面ショットを好んだマノエル・ド・オリヴェイラによる画面の強度にまで達している、とだけはかろうじていえるだろう。正面ショットのみならず、黒沢清は、長い独白を含む一連のシーンを、現代日本映画の環境においてはこの上ない最善のショット構成で捉えることに成功する。撮影監督の芦澤明子のキャメラワークと、フジエを演じる村岡希美の演技は、複雑な長回しも含む監督の要請に見事に応えている。2010年代日本映画の最高の達成がここに現前している。
フジエの妹は、はじめて最後まで完璧に『天使の合唱』を弾き終えると、瑞希の方へ振り返り、少し照れているようなぎこちなさで笑みを浮かべ、姿を消してしまう。広間に陽光の明るさが戻る。小鳥のさえずりが聴こえる。
続くシーンで展開される、優介の浮気相手であった松崎朋子と瑞希の対話は、わずか5分ほどのごく短いものであるにも関わらず、見る者に鮮烈な印象を残す。東京に帰るバスの中で、朋子からの葉書を瑞希のカバンの中にみつけた優介と痴話喧嘩を繰り広げる瑞希は、ついに激昂し、わだかまりを残し続けていた問題に対して感情を爆発させ、朋子に会いに行く決心を固める。
東京では歯科医として働いていた優介の職場である病院のロビーで落ち合った瑞希と朋子の会話は、横移動しつつのマスターショットと肩ナメの切り返し、そして正面切り返しというシンプルな構成でありながら、成瀬巳喜男を彷彿とさせるような一人の男をめぐる二人の女の辛辣な台詞の応酬と、朋子を演じる蒼井優の悪魔的な演技によって一度見たら忘れられないほど強烈な印象を観客に叩きつけてみせる。とりわけ、あなたに夫婦関係の複雑さは理解できまい、と抗議する瑞希に対して、自分も結婚しておりさらには妊娠中の身でもあることを明かす朋子の正面ショットでは、不敵な微笑を湛えた彼女の瞳の奥にギラつくどす黒い何か、究極の深淵とも呼べそうな何かに思わず吸い込まれてしまいそうになるほどだ。たった5分ほどのシーンで、蒼井優は『岸辺の旅』の中で誰よりも印象に残る演技をみせつけるのである。
「きっとこれから、死ぬまで平凡な毎日が続くんでしょうね。でも、それ以上に何を求めることがあります?」
計らずも深淵を覗き込んでしまい、朋子に一矢報いることもできぬまま家路につくが、そこに優介の姿はなく、またも生の熱量を失いかける瑞希は、突然目を見開き、慌ただしく白玉団子を作りだす。こうすればきっと優介はまた帰ってきてくれるに違いない。瑞希はテーブルに二粒の団子を用意し、それを凝視しつつただじっと座って待っている。すると突然、薄暗いキッチンのテーブルの上に団子があるだけの映像にオーケストラの劇伴が流れはじめる。クラリネットとファゴット、そしてフルートが、歓びを高めてゆくような、控えめなファンファーレのような旋律を告げるのだ。瑞希は歓喜に打ち震えるように瞳に涙をため、吐息を震わせ右斜め上方をみつめる。視線の先に優介が現れたのか。そうではない。瑞希の顔は後ろへ振り返る。しばらくの間ののちに、やはり靴を履いた足音で優介が奥の部屋からゆっくりと姿を現す。
奇跡を予告するように劇伴が先回りして流れはじめるという例なら他にもあるだろう。しかし、ここで信じがたいのは、瑞希が劇伴を聴いているということだ。映画の中の人物が劇伴を聴いてしまうという、暴挙としか言いようのない事態がここで起こり、それによって瑞希は観客と同時に優介の再臨を「予感」するのである。
この暴挙とよく似たショットを持つ映画をご存知か。ジョン・フォードの『駅馬車』である。あの名高いインディアンの奇襲の場面。壮絶な銃撃戦が続くが、応戦するための銃弾が尽きた。残るはたった一発のみ。多勢に無勢。万事休す。男は頭の皮を剥がれ、女はインディアンの嫁として連れ去られるだろう。絶望極まれり。せめてもの情けとして最後にできることといえば、残された銃弾で女をあの世に送ってやることぐらいしかあるまい。恐怖のあまり精神の均衡を失い、何やらぶつぶつ呟いている女の頭部に男は拳銃の先を向け、撃鉄を起こすが、インディアンの銃弾の方が一瞬早く男を貫く。男の手から拳銃がこぼれ落ちる。すると、どこからともなくラッパの音が鳴り響く。女は、その先には何もないはずの右斜め上方へと視線をやる。
「ねえ、聴こえる?あの音が。ラッパよ、突撃ラッパよ!」
女が精神の均衡を取り戻し、騎兵隊の救助の手が間一髪で間に合ったことに気づくこのショットで、「突撃ラッパ」は、音響の質的に戦闘の最中鳴り続けていた劇伴の展開の一部として聴こえるように処理されている。この時代の技術であっても、例えば劇伴の音をフェードアウトさせ、「突撃ラッパ」だけ鳴らすことで現実音として観客に分かり易く解釈させることも可能だったろう。しかしここでは、女の表情と台詞によってその音が意味するところを伝えるために、あえて劇伴と「突撃ラッパ」を区別させない音響の演出が実践されているのだ。つまり、『駅馬車』においても『岸辺の旅』同様に、映画の中の人物が半ば劇伴を聴いてしまっているのである。劇伴を聴き、その先には何もないはずの右斜め上方をみつめる二人の女。この類似を単なる偶然の一致として済ませてしまってはなるまい。

4.「また、会おうね」
二人が最後に訪れる場所は、優介が私塾を開いていた山奥の村である。村で二人の住居を世話することになる快活な老人、星谷(柄本明)の孫である良太(藤野大輝)は、森の中にある夫婦滝を気に入っており、学校を抜け出してまで遊びに行くほどだという。ある日、良太の母親である薫(奥貫薫)が良太に弁当を持たせ忘れ、瑞希が届けることになる。学校にいないのなら、きっと滝です。よく行ってるみたいなんです。何が面白いんだか。
瑞希が滝を訪れると、やはり良太がそこにいる。良太は弁当に関心を示さず、夫婦滝の伝承について話しはじめる。
「あそこの黒い部分見える?洞窟、あれね、死んだやつの通り道なの。あの世とつながってんの。ほんとだよ」
「そうか、あの人はここから来たんだ」
瑞希は、優介が現世に帰還した謎について思いを馳せる。あくる日またも弁当を良太のもとに届けることになった瑞希は夫婦滝を再訪するが、そこにいたのは良太ではなく、亡くなったはずの瑞希の父親(首藤康之)であった。
ここで想起させられるのは、ロバート・ゼメキスの『コンタクト』である。『コンタクト』でジョディ・フォスターが演じる地球外知的生命体探査プロジェクトの研究者もまた、瑞希同様早くに父親を失うが、彼女がついに遭遇した地球外知的生命体は亡き父の姿を借りて現れたのだった。瑞希が滝で父と再会するのに対し、『コンタクト』での遭遇は浜辺である。いずれも水辺を舞台として超越的なシーンが演じられているのである。さらにこの類似は、再開した私塾で、優介が光や宇宙をめぐる講義を行うことともつながるだろう。
「きっと宇宙ははじまったばかりなんです。みなさんは幸運にも、この誕生したばかりの若々しい宇宙に生まれることができました。これって凄いと思いませんか。計算によると、28億年後には、地球の温度が140度まで上がって人が住めなくなり、40億年後には銀河系とアンドロメダ銀河が衝突することになるんですが、まあこれはほんの些細な出来事なんでしょう。宇宙はこれで終わるんじゃない。ここからはじまるんです。我々はそのはじまりに立ち会っているんです。俺はそう考えるだけで、すごく感動します。生まれてきて本当に良かった。それがこの時代で、本当に幸運でした」
一方『コンタクト』で地球外知的生命体と遭遇を果たしたものの、記録機器の異常によって証明が不可能となり、彼女の遭遇体験が妄想によるもので実際には宇宙にすら行っていないと政府委員会から糾弾されるジョディ・フォスターは、瞳に涙を湛えながら次のように抗弁する。
「経験したのは確かです。証明も説明もできません。けれど、私の全存在が事実だったと告げています。あの経験は私を変えました。宇宙のあの姿に、我々がいかに小さいかを教わりました。同時に我々がいかに貴重であるかも。我々はより大きなものの一部であり、決して孤独ではありません。そのことを伝えたいのです。そして、ほんの一瞬でもみんなに感じてもらいたい。あの畏敬の念と希望とを」
『岸辺の旅』での講義と『コンタクト』での政府委員会の両者に共通するのは、それが単なる宇宙論ではなく、映画体験をめぐる挿話として読み替えることができる点である。
映画見ることとは、1秒間に24コマもの速度で流れ去るフィルムを通過し、巨大なスクリーンに反射した光の絶え間ない蠢きを視て、また同時並行的に絶え間なく流れ続ける音響を聴きもするという人間の知覚の情報処理能力を遥かに逸脱した体験に他ならない。ひとりの人間の視覚と聴覚がそれらの全瞬間を認識し、記憶することなど不可能である。そのような本来的に不可能性を孕んだ個人の映画体験なるものを客観的に正当化し、証明し、説明することなど誰にもできはしない。光などしょせん質量0の、ほとんど無に等しい粒の集合体でしかなく、光から成る映画などしょせん無が織りなす単なる幻想でしかないと言われればそれまでだろう。
しかし「私」という主観は確かにそれを「経験」した。人間の魂と、それを包み込む愛としか呼びようのない何かがそこには確かに映っていた。その事実を、いまこの瞬間も「私」の「全存在」が告げている。その有様に「我々がいかに小さいか」、「我々がいかに貴重であるか」、そして同時に我々がいかに「孤独」でないかも教わった。その「経験」は「私」という存在を変化させもした。
宇宙の歴史と比較するまでもなく、この世に生まれてからたったの126年ほどしか経っていない映画は「これで終わる」のではなく「ここからはじまる」。いままさに「我々はそのはじまりに立ち会っている」。
現世での存在の終わりを迎えつつある優介は、苦痛に蝕まれながら村での役目を果たすと、瑞希に支えられながら、とある浜辺を訪れる。そこはおそらくは優介の本来の身体が眠っている海なのだろう。これから「ここよりももっときれいな場所」に行くという優介に、行かないで、うちに帰ろう、と懇願する瑞希は、優介の身体を強く抱きしめる。空を舞う鳶の影が横切る。
「ちゃんと謝りたかった。でもどうやって謝ればいいのか、ずっとわからなかった」
「望みは叶ったよ」
「そうか」
「また、会おうね」
「うん」
会話を終えると、優介の姿は消えた。瑞希は、その時が来たら燃やす約束だった100枚の祈願書に火をつけた。瑞希は振り返り、荷物を抱え歩き出した。キャメラはゆっくりと上昇し、入り江の岩や樹、海と空を映した。よく晴れた日だった。
M.K.へ
(スタッフT.M.)

(C)2015「岸辺の旅」製作委員会/COMME DES CINÉMAS
※ご留意事項※ 将来、テキストや画像をクリックし、飛び先がリンク切れになる場合は、配信期間が過ぎ終了した為です。ご了承いただけると幸いです。